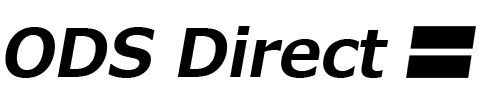- 法人・業務用タブレットTOP>
- >
- タブレットの導入でドクターカーやドクターヘリとの連携もスムーズに
|
事故や火災などが引き起こされた現場では、人命が最優先されます。
その際に活用され始めているのが、ドクターカーやドクターヘリです。速やかに現場に急行することで、応急処置を行い、人命救助に大いに役立つ働きを見せています。 しかし、出動するためには、事故の状況や現場の正確な位置を特定することが重要で、正しい情報を集めなければ対応が遅れてしまう可能性もあるのです。 その中で活躍を見せているのが、タブレットによる救命救急支援システムです。 実際にはタブレットの活用で、どのような効果が発揮されているのでしょうか。 |
 |
|
■事故発生からドクターヘリの要請時間を短縮 通常の事故であれば、ドクターヘリが出動して治療が開始されるまでは、平均で38分かかるといわれています。事故発覚から消防が覚知するまでに5分、ドクターヘリの要請までに15分、治療開始するまでに18分の内訳です。 人命救助には、1分1秒でも早く現場に到達するのが重要です。 そのために導入されたのがタブレットでの「救急自動通報システム」と呼ばれるものです。 救急自動通報システムでは、エアバックが作動したことで、車両情報やGPS情報などが管轄の消防署に伝わるシステムになっていて、ドクターヘリが出動する被害か判断されるのが特徴です。 ドクターヘリに搭載されている専用タブレットで消防署から送られる情報を基に、現場に向かい、速やかに救命活動を行えるような仕組みになっています。 タブレットによる救急自動通報システムを導入することで、事故発生からドクターヘリ要請までの時間を短縮し、合計20分かかっていた時間を3分に短縮が実現できました。 速やかに現場に到達しなければならない緊急時にとって、17分の短縮は大きな進歩といえるでしょう。 ■効率的なドクターカー出動が可能になった 救急車と違い、医師と看護師が乗車しているドクターカーは、迅速に救急現場に到達することで、人命救助に大きく貢献することが可能です。 ドクターカーに専用タブレットを搭載し、医療機関と連携を取ることで、事故現場写真や目的地、経路などの情報を共有し、速やかにドクターカーを現場に誘導する働きがあります。 渋滞情報も共有することで、短い時間で現場に向かうことができ、適切な応急処置を行うことができるので、緊急性が高い医療現場で専用タブレットを使用することは大きなメリットといえるでしょう。 他にも、病院と連携を取ることも容易です。患者の受け入れなどを要請することもタブレットで情報を補うことができます。 事故現場や火災現場などで、状況を把握することは、人命救助を行うためには必要不可欠な情報です。 ドクターカーにタブレットを搭載することは、生存確率を高める方法として大いに役立っているのです。 |
| * * * * * |
|
【まとめ】 今まではドクターヘリやドクターカーが現場に急行しても、現場状況をその場で把握するということが多く、予想外の出来事が起きるといった問題が多くありました。 しかし、タブレットによる救急自動通報システムを導入することで、事故発生の要請を速やかに受け取ることができ、速やかな対応が可能にすることができます。 また、タブレットに写真や動画といった現場の情報を共有することで、現場に急行する前に、状況を把握することが可能です。これにより、人命の生存確率が向上に大いに貢献しています。 今後もタブレットが医療現場で活用されていくことが予想できるので、さらに普及率が高まることに繋がるでしょう。 |