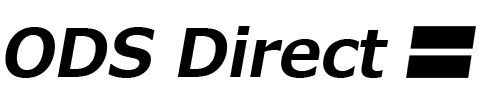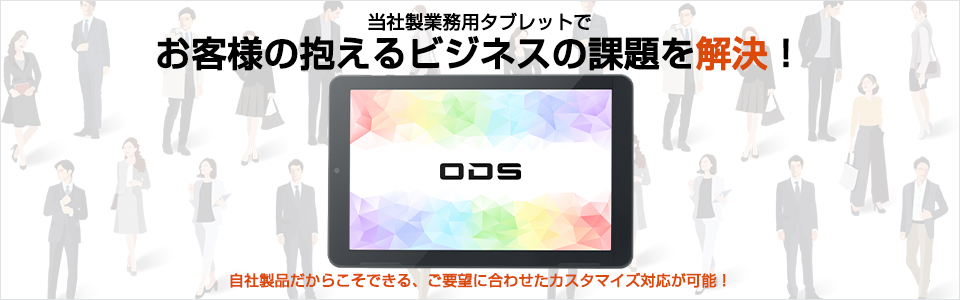- 法人・業務用タブレットTOP>
- >
- 市役所などでもタブレットを使った遠隔手話通訳が導入されている
 |
| Facebook Twitter |
|
耳の不自由な方が窓口サービスを受ける場合、意思疎通を図ることが難しい場合があります。 対応する側もどのように対応すればいい良いのか、迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。 自治体では、手話通訳の資格を持っている方が対応することは可能です。しかし、その都度窓口に通訳をしに行くのは難しいことでしょう。 そんな時に導入が検討されたのがタブレットによる遠隔手話通訳です。上手く活用することで、離れた場所から手話通訳を行うことができます。 今回は、タブレットによる遠隔手話通訳について解説していくので、参考にしてみてください。 |
目次耳の不自由な方は、公的なサービスを受ける時、コミュニケーションをとることが難しい場面もあると思います。 市役所などでは、本庁の専門部署に手話通訳を常駐させることで、耳の不自由な方がサービスを受けられるように手配をしています。 しかし、実際には全体の自治体にこの制度が行き届いていないのが難点です。 各支所に手話通訳の資格保有者が巡回する対策も検討されていましたが、そのためには財政面や業務面で負担ということから実施されることはありませんでした。 そのため、今でも公的サービスを満足に受けられない方が多く、この対策を講じようと画策している自治体が多くあるのも事実です。 ■タブレットのビデオ会議システムで遠隔手話通訳が可能 耳が不自由な方のために講じられた対策が、タブレットを用いたテレビ会議システムの導入です。窓口にテレビ会議用のモニタを設置して、窓口と手話通訳者とを回線で繋げることが可能です。 手話での通訳が必要になった時、窓口担当者と利用者がモニタの向こう側にいる手話通訳者を通して意思疎通を図ります。 このシステムを利用することで、最小限の人件費でのやり取りが可能になり、耳の不自由な方に充実したサービス提供ができるようになりました。 このようなテレビ会議システムは、耳の不自由な方がストレスなく手続きができるよう他の公共機関でも導入が検討されています。 ■銀行などの窓口にも導入が検討されている 今まで耳が不自由な方が窓口担当者ととっていたやり取りは主に筆談です。 筆談だと確かに誰でもコミュニケーションはとれます。しかし、書いている時に間が空いてしまったり、急いでいるときには時間がかかりすぎたりと、スムーズなやりとりはなかなか望めません。 タブレットの導入によって、耳の不自由な方でも今までよりも気軽に窓口サービスを利用できるのではないでしょうか。 今後は銀行などの窓口でも、タブレットを通したテレビ会議システムの提供が検討されているので、タブレットの導入によりさらに快適なやりとりが期待されるでしょう。 |
| * * * * * |
|
【まとめ】 市役所などで導入されつつあるタブレットを用いた遠隔手話通訳。 耳の不自由な方が手続きを行いやすいように対処されているだけでなく、手話通訳者の負担も軽減できます。 自治体全体で導入されれば、公的サービスをさらに、円滑に受けることができるようになります。今後の自治体同士の連携が重要になってくるでしょう。 |